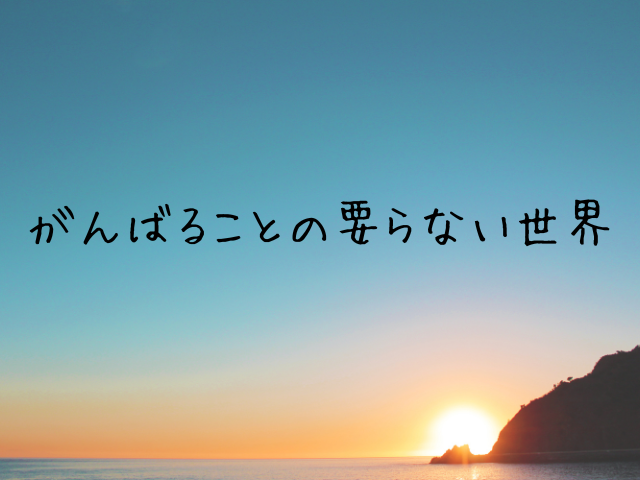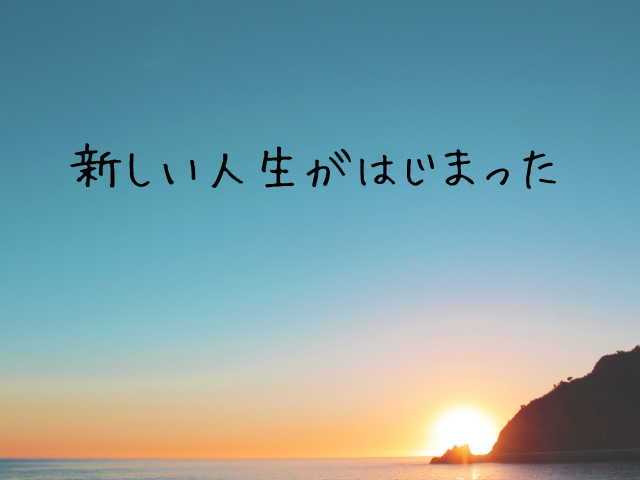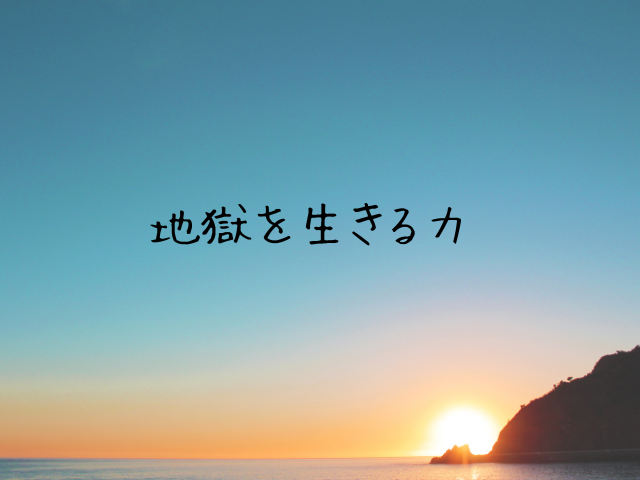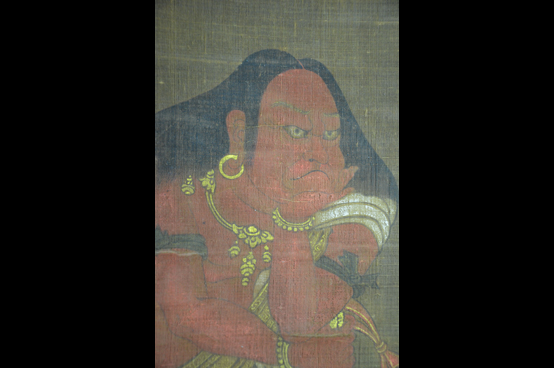「『がんばって』という言葉を、よくお見舞いの方から耳にしますが、『がんばれ』『がんばれ』のオンパレードはたまりません。患者は誰も皆がんばっているんです。『がんばれ』の乱発は、患者にとって失礼だと思います。」ある仏教ホスピス(ビハーラ)の活動をしているグループの集会に参加したときに、癌の告知を受けた女性がこう語ってくれました。
お見舞いに行かれたご本人が意識しているかいないかは別として、それが同情やあわれみであるなら、患者さんにとっては煩わしいものでしかなく、むしろ見舞った相手が健康を誇っているようにさえ感じられてしまうのではないでしょうか。なぜそうなってしまうのか。同情やあわれみは、結局は相手のことを、自分とは違う「かわいそうな人」「お気の毒な人」としてしまうことになり、そしてそこには微妙な上下関係すら生じてしまうのではないでしょうか。
特に癌の患者さんの場合、『壮絶癌死』などの言葉に代表されるように、心身ともに苦しみの中にある気の毒な人として見られる社会があることと、そのなかで患者さん自身もこの病気を患ったら不幸以外の何物でもないという価値観しか持ちにくいことが、本当の意味での不幸であるように思います。
同情やあわれみも、人としての美しい心なのかもしれません。しかし、その一片のあわれみにも常に功利や打算が混じってしまう私たちであり、それを徹底することができない私たち自身が問題なのでしょう。そういう自分を教えられることによって、かろうじて人と共に生きる心が保たれてくるのではないでしょうか。
私たちは、正直なところ、やはり「自分が一番かわいい」という思いで生きています。どのように立派なことをいい、行動していたとしても、その裏には必ず「差別的」で「自己中心的」な心が隠されているようです。そのような自分の内面に目が向くことがあったとしても、たいてい「凡夫だから…」などといって自分でごまかしています。しかし、不思議なことに、人間はそういう自分の姿に本当に気づかされたとき、悲しみや空しさを覚えるものです。実は、そうした感覚の根元にあるものこそ、「如来からのはたらき」として教えられていることなのではないでしょうか。
袈裟・衣を身にまとい、日頃まことしやかに仏法を語っている私ですが、一方で「本当におまえ自身が生死無常の理(ことわり)に立って語っているのか?」「わかっていないものに聞かせてやろうというような根性がありはしないか?」と、問い返されるものがあります。そうした声なき声に叱咤され激励されるからこそ、少しずつ歩んでいけるような気がしています。
誰に代わってもらうこともできない、一度きりで、いつ終わるとも知れない有限なこのいのちです。だからこそ「がんばれコール」で終わるような出会いではなく、「私も共に死すべき身です」と言葉を超えて通じていけるような出会いをしてゆきたいものです。
平松 正信(ひらまつ まさのぶ 東京都新宿区 専行寺住職)