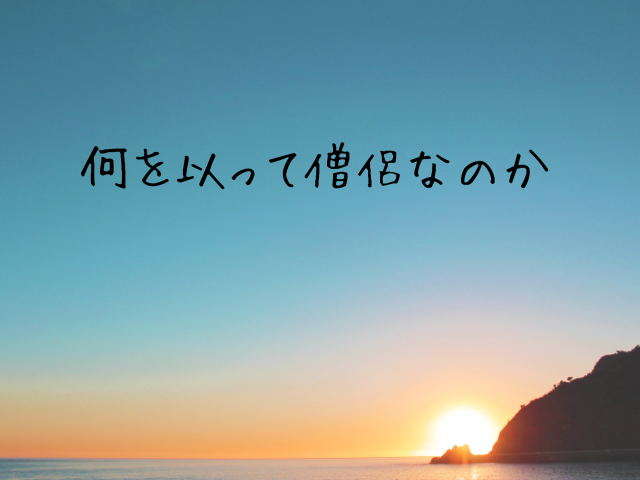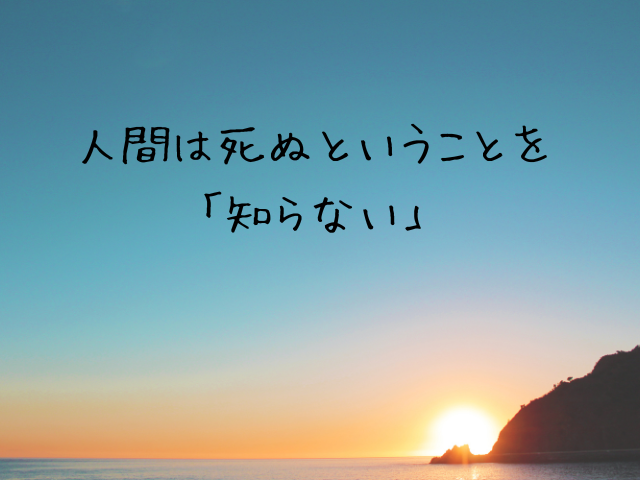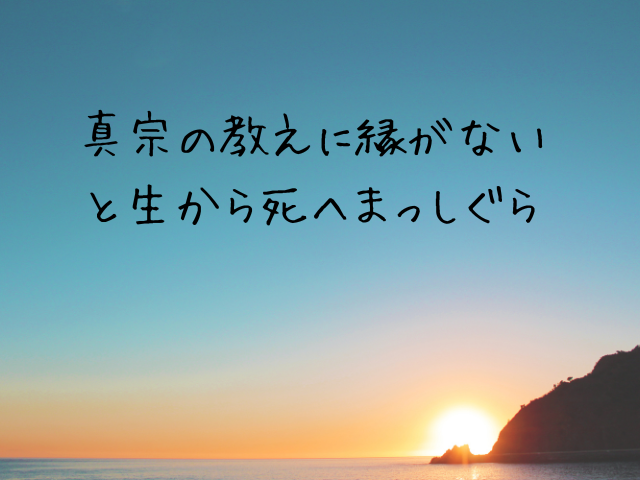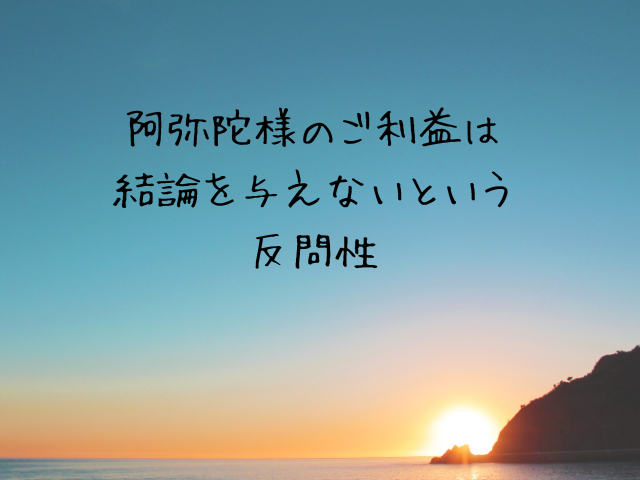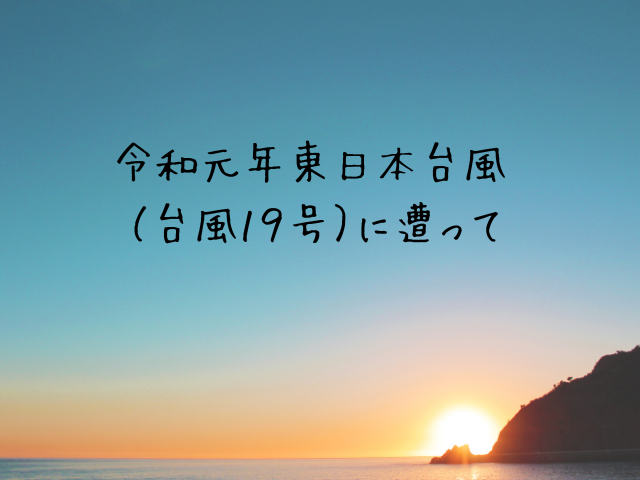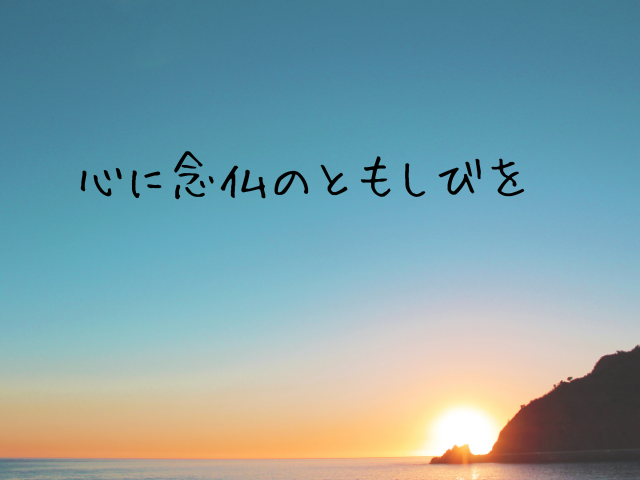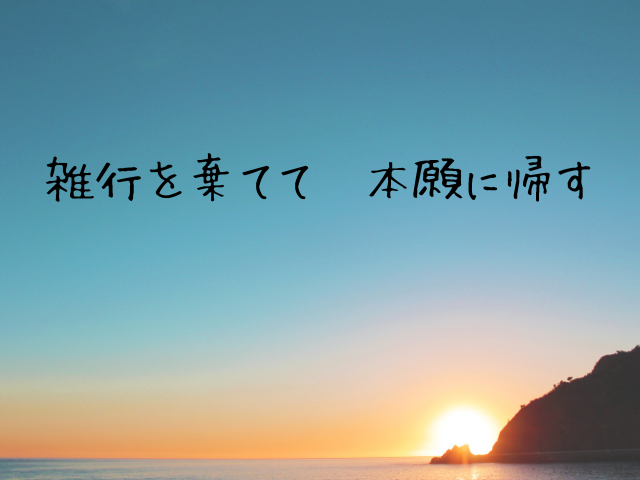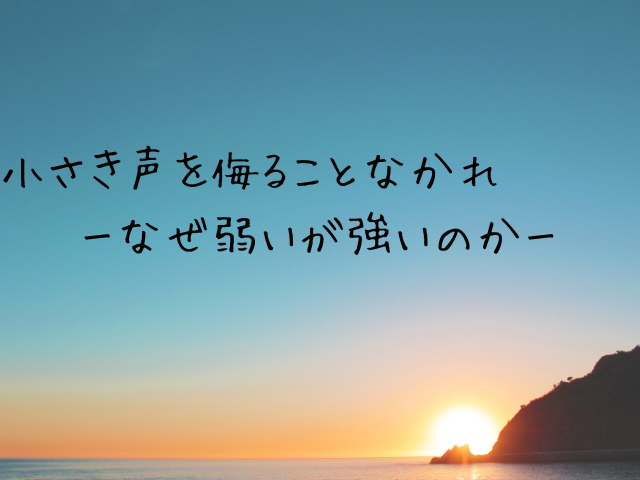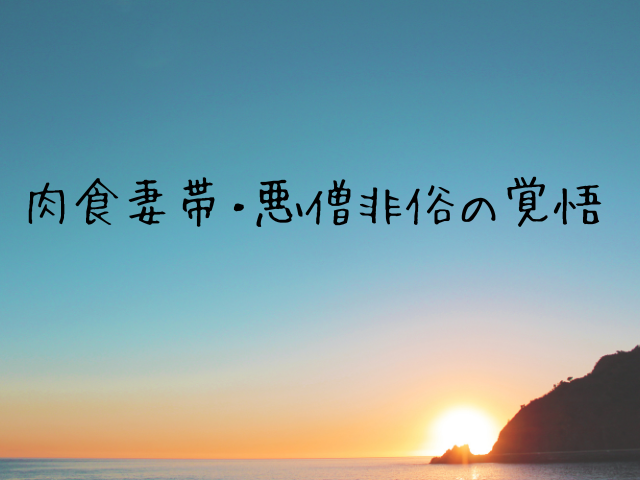この言葉は特別講義にて曹洞宗・恐山菩提寺院代である、南直哉先生が講義中にふと口にされた言葉です。「何を以って僧侶なのか」と。この言葉を聞いたとき私はいつ僧侶になったのだろうかと思い起こしました。
私は母方の実家が寺であり、前住職の孫として生まれました。9歳の時に祖父と祖母に連れられ、京都の本山で得度式を受式したことを覚えています。正直なところ当時の私は何もわかっていませんでした。宗祖が親鸞聖人であることも知らなかったですし、どうして同じくらいの年齢の子たちが一緒になって剃髪をして並んでいるのかも、よくわかっていませんでした。ですが私の僧侶としての出発点はいつなのだろうかと考えたとき、やはりこの得度式を受式したことが思い浮かぶのです。
それから大谷専修学院に入学して真宗大谷派教師資格を取得させていただき、自坊に戻り5年が経とうとしていますが、私は先生が言った「何を以って僧侶なのか」なんて考えたこともなかったのです。そこで自分が無疑問的に僧侶であると思っていたことに気付かされました。問いを持っていなかったのです。
私が僧侶としていまここにいるということは様々な出遇いがあったということです。教学館通信のタイトル「私が出遇った言葉」のなかで使われている、「遇」という言葉には「であい、めぐりあい」また、「たまたま、思いがけなく」という意があります。私の人生を過ごす中においても、たくさんの出遇いがあったはずです。しかし、私はその多くを必然的にとらえ、またその出遇いから関係性が続くと、今度はそれが当たり前に変わり、どこか、たまたま出遇えたということの有り難さを忘れ、なおざりにしていました。であっているのに出遇っていない、そんな、ちぐはぐな生活が私の日々の中にあるのです。
「何を以って私は僧侶なのだろうか」この問いに対して、はっきりとした答えを持つことはこれからもないかもしれませんが、私が僧侶として生きていく中で大切に維持していきたい言葉でした。
『Network9(2024年1月号)より引用』内藤 友樹(東京1組 光桂寺)