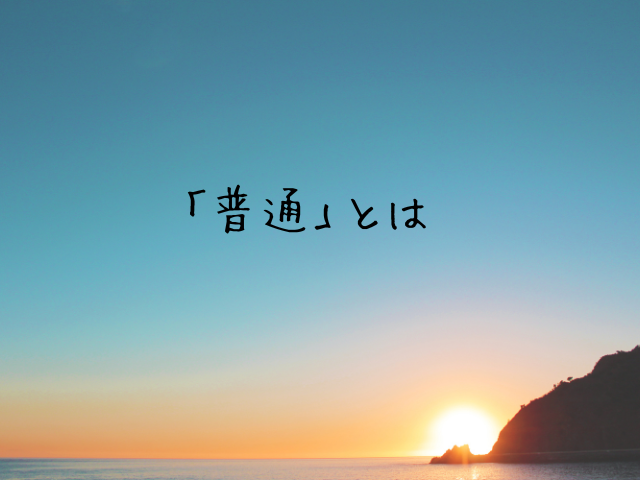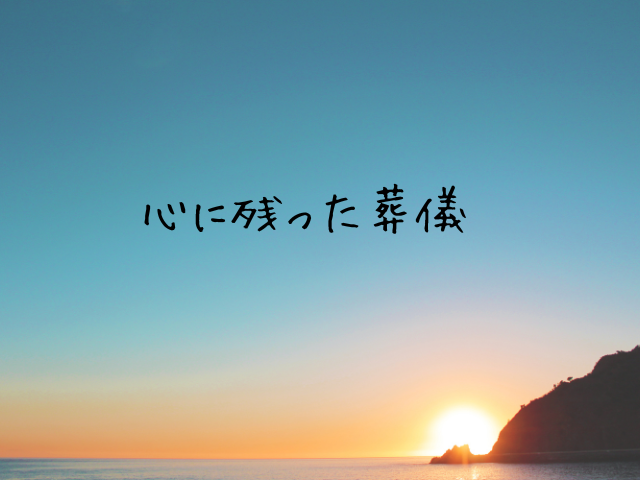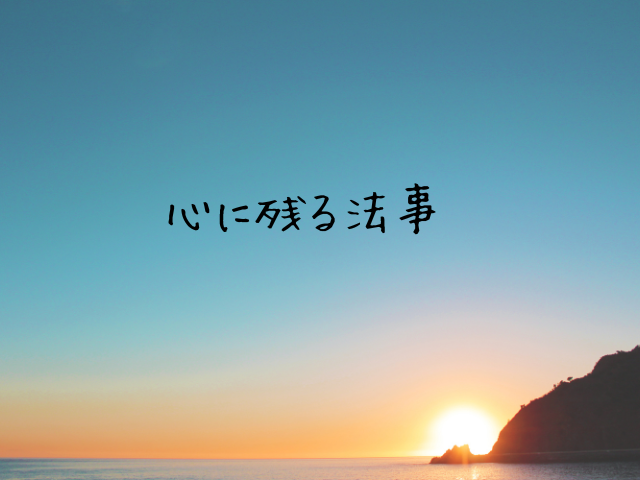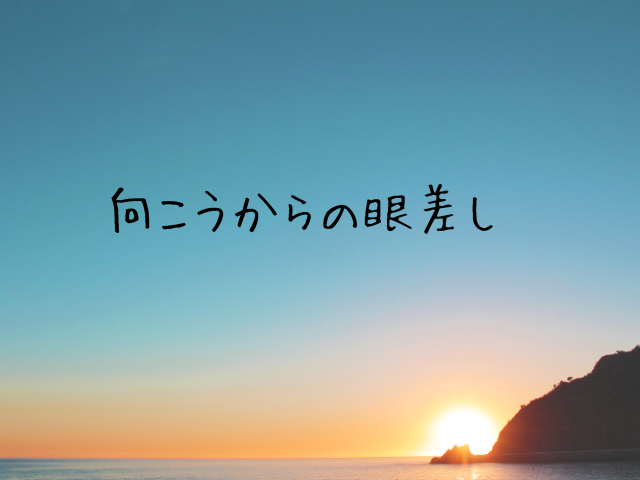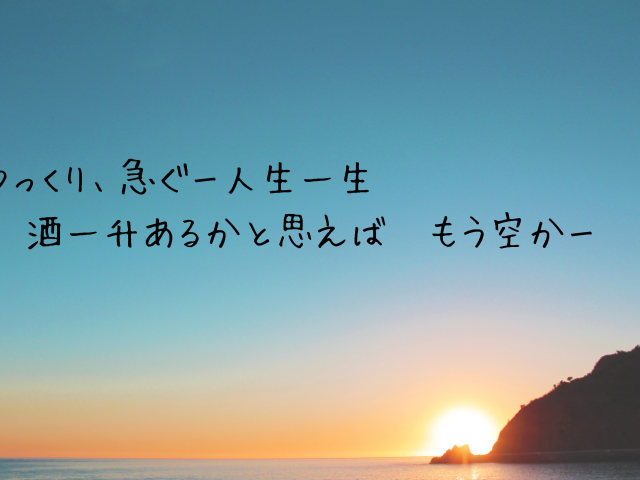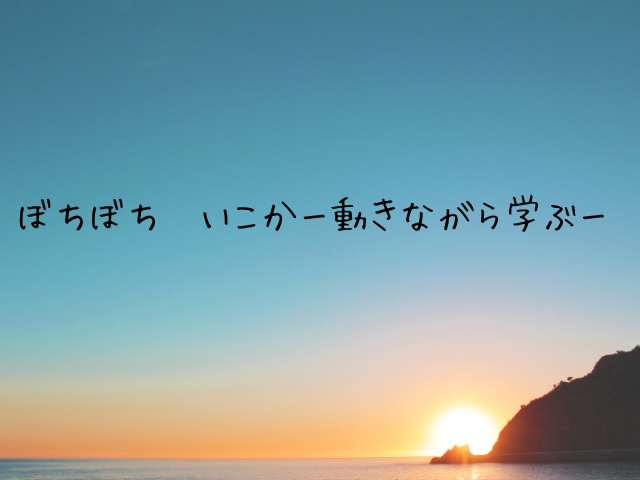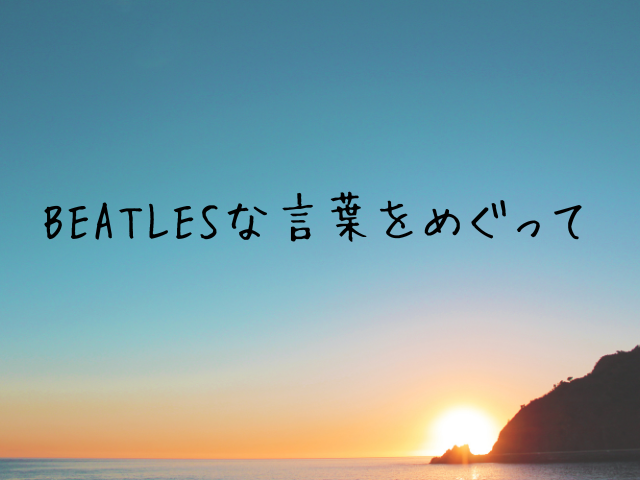猫は一日に18時間くらい寝るそうです。いつもうらやましいなぁと思いながら、寝姿を眺めています。人間は、ひとによって睡眠時間はまちまちです。7時間以上寝ないと、短命になるとか、寝過ぎてもいけないとか、いろいろにいわれています。
能科学者・茂木健一郎が、「なぜひとは眠るのか」について話していました。
脳は起きている間、新しい情報を受け取りつづけているそうです。昼間は、情報の受け入れに手一杯で整理する時間がありません。そこで、脳は、眠ることによって、昼間に得た膨大な量の情報を整理するそうです。ときには、昼間以上に活発にはたらいているそうです。ですから、脳に休暇はないのです。脳は、休憩のために眠るのでなく、昼間とは違った仕事をするために、「眠り」というモードへシフトチェンジするのです。
また、脳の得意なことは、たんなる記憶ではなく、新たに得た情報から新しい意味を発見することだと言っていました。記憶力では、とてもコンピューターにはかないません。
そういう私もコンピューターにお世話になっているひとりです。たとえば「浄土」という文字が、親鸞の主著である『教行信証』にいくつ使われているかなど、瞬時に調べることができます。(ちなみに119回です)しかし、コンピューターは、文字の関連性から思想を組み立てることはできません。
これらの話を聞いたとき、「眠ることは、脳を休めるため」という考えが間違いだと教えられました。このような脳のはたらきを、親鸞は「憶念」といったのではないでしょうか。親鸞は「憶念は、信心をえたるひとは、うたがいなきゆえに、本願をつねにおもいいずるこころのたえぬをいうなり」(『唯信鈔文意』)と述べています。「本願をつねにおもいいずるこころのたえぬ」が、「憶念」にあたると思います。
以前、私はこの表現を譬喩だと思っていました。「つねに」は、目覚めている間のことで、寝ているあいだは無理だろうと。ところが茂木健一郎の話を聞くと、まんざら譬喩でなく、現実に脳がおこなっている作業が、「憶念」だとわかりました。ただし、寝ている間も憶念が継続するためには、目覚めいてる間、十分に課題を考えておく必要があります。親鸞は「本願」について、昼間、十分に考えていたのだと思います。
親鸞は、夢の告げを大切にします。ただ、現代人とは夢の味方が違います。現代人は眠ったとき、たまたま見るのが夢です。親鸞の夢は、ある課題を昼間考えつづけ、夜は、「告げを受けるため」に仮眠している状態で見るのです。そこには覚醒時の脳と就寝時の脳との共同作業があります。どちらが欠けて「憶念」にはならないのでしょう。
しかし、覚醒時の脳では、なにも考えていないように見えて、就寝時の脳がフルに考えていることがあります。覚醒時の脳は、些細なこととして忘れていても、就寝時の脳がしつこく考えていることがあります。あるときフッと、「おれが気になっていたのは、このことだったんだ」と気づくことがあります。日ごろは雑事に紛れて忘れていても、就寝時の脳は決して忘れません。人間のこころは不思議なもので、自分にとっては、まだまだ未知の世界です。
今日も、私はスーッと眠りに落ちます。いつ眠ったかを知らずに眠ります。これは「死」と同じ形です。「死」も「眠り」と同様に人間には自覚できません。眠りは「死」の予行演習です。できたら、本番も、スーッとであったらいいなと思います。
武田 定光(たけだ さだみつ 東京都江東区 因速寺住職)

![眠りと憶念[おくねん]](https://staging-jinnet.kinsta.cloud/wp-content/uploads/2024/10/17.png)