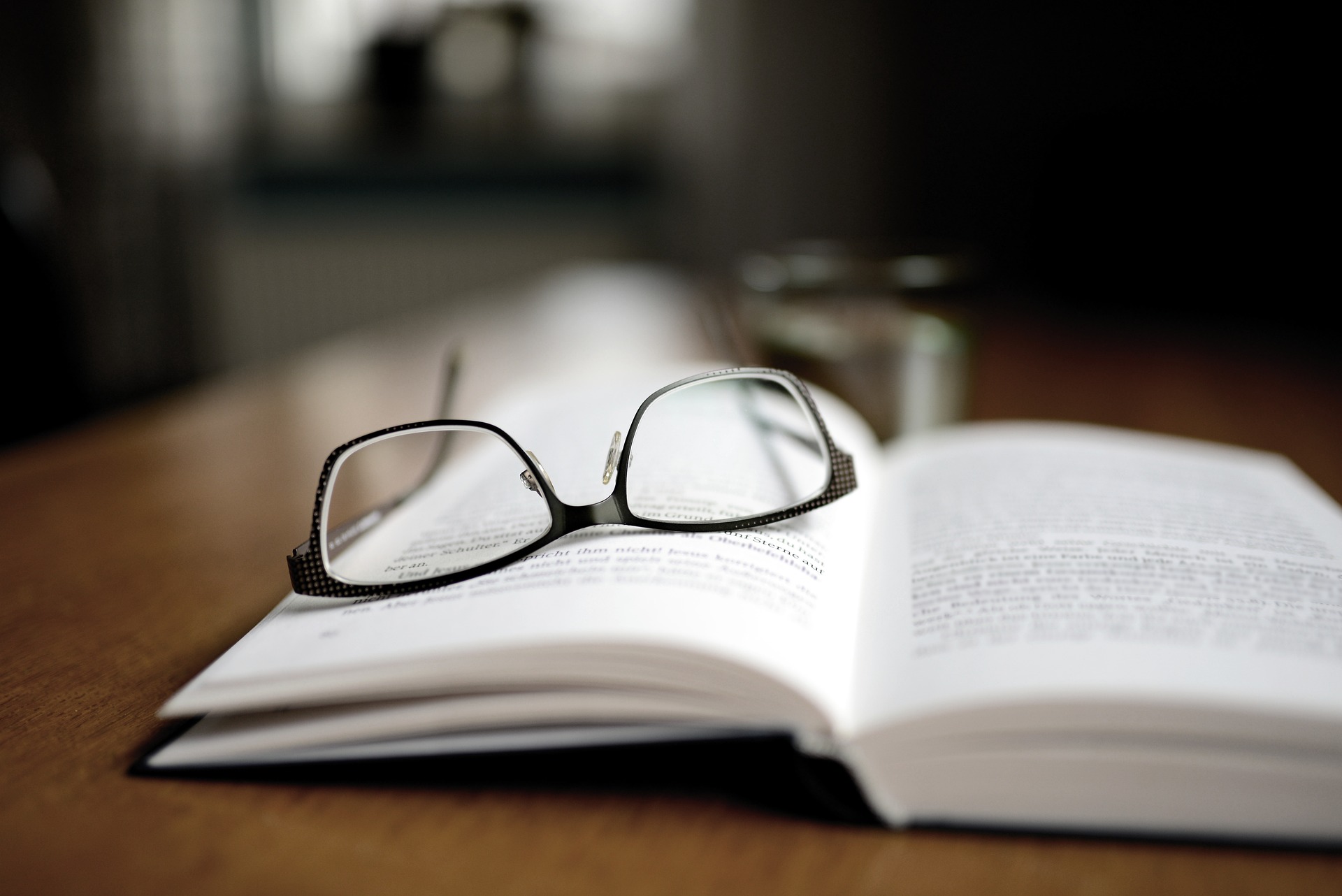毎年、8月のキーワードは「戦争」である。2019年に亡くなった加藤典洋さんは、「戦後世代に戦争責任はあるのか」という問いを立て、「それは、『ない』ということから考えていっていい、『ない、しかし、引き受ける』というみちすじのありうることを明らかにすることがここでは大事だ」(『戦後を戦後以後、考える』岩波ブックレット)と述べている。その理由として、「罪の自覚は、その個人の行った行為に関する罪でない限り、必ず彼の帰属する集団への共同的ないし公共的連帯感を基礎にするからです」と。だから「彼らにまず罪の意識を根づかせようというこの試み(戦後世代にも罪があるとする主張〔武田補記〕)は、必ず顚倒した形でしか彼らに届かないことになるのです。それは、一種の強迫観念となって、彼らの中に生きるしかない」と。
加藤さんは「戦争責任はない」と名言することが、「ある」を成り立たせる「足場」であり、この「足場」を確保するとき、主体的な選びとして「ある」が成り立つ可能性があると言う。
更に、「罪の意識からはじめるというのはダメで、むしろ、この『人間として』という意識がどこから生じるか、ということを先にして考えていかないと、この罪の意識の問題も解けないのです。『世界を引き受けるとはどういうことか』と言いましたが、この意味ではそれは、『人間として』という意識を人はどのようにもつことになるのか、ということだと言ってもいい。」と述べる。
加藤さんの「人間として」という提起は、「戦争」を過去の出来事にせず、未来をも視野に入れた発言だと思う。まさにいま起こっている、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルとハマスの戦いが、それを証明してしまった。「戦争」は「悪」に決まっている、それであっても、懲りずに「戦争」を起こす「人間」の構造を、未来の問題として考えなければならない。つまり、「私の問題」として。これが未来の問題となったとき、初めて「戦後以後に生まれたひとびと」をも包んだ課題となるのではないか。
そもそも、人間が、突き詰めれば、私が「貪欲 rāga」という煩悩で出来上がっている以上、未来にも「戦争」を起こし得る可能性をつねに秘めている。だからこそ、この「貪欲」の騙しを見破り続けなければならない。「貪欲」の構造が明確に「対象化」されるとき、「一切衆生の中の特殊な自己」と異質な、もう一つの自己、つまり、「一切衆生の典型としての自己」が誕生する。これが加藤さんの言う、「世界を引き受ける」という言葉が指し示す「足場」となるだろう。
東京6組 因速寺 武田 定光 師『東京教報』 187号 巻頭言(2024年10月号)