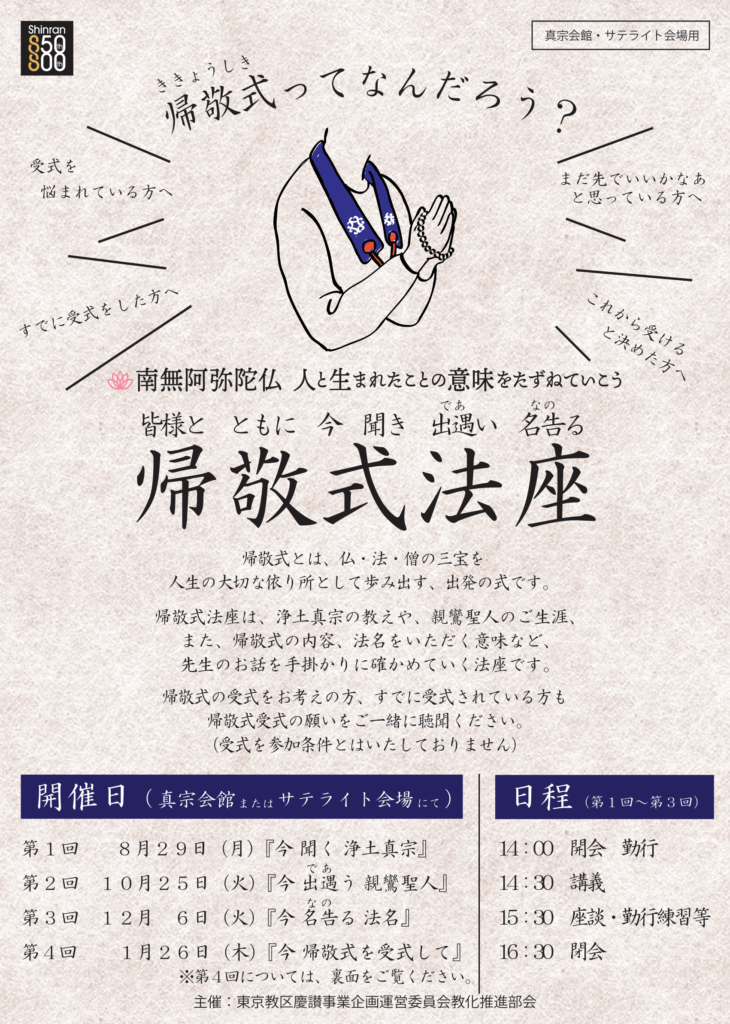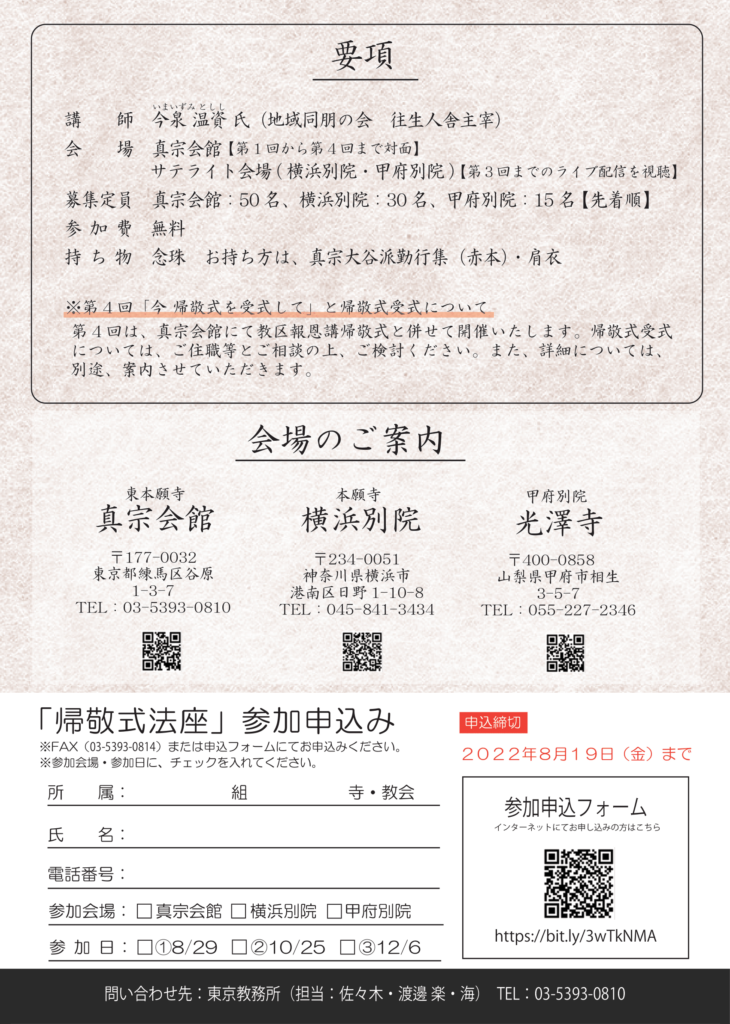葬儀や年忌法要などの仏事のときにいただく食事を「お斎(おとき)」といいます。お亡くなりになった方を偲びながら、僧侶や久しぶりに会う方とお話しし、列席された方への感謝を表す場でもあります。そのようなお斎ですが、本来の意味や宗派によっては作法があるということをご存知でしょうか。食事をすることや準備をすることに気を取られやすい「お斎」ですが、本来の意味や作法を知ることで、その時間を一層豊かに過ごすことができるのではないでしょうか。ここでは、様々な「お斎」の疑問について応えてまいります。
そもそも「お斎」ってなに?

「お斎」という言葉は仏教教団の生活の決まりからきた言葉です。
「お」は丁寧語で、「とき」というのは「時」のことで「決まった時」にとる食事のことを指します。具体的にはお昼の食事のことで、朝食と「時」以外の食事は「非時」と言います。そういった決まりのことを「斎」(さい)といいました。そこから斎=ときとなったと考えられています。現代では、仏事の際に取る食事のことを言います。
真宗大谷派では、報恩講(親鸞聖人のご命日に勤める法要)などの仏事の際に、お参りされる方、お一人おひとりが、米や野菜などを持ち寄り、調理していただいた食事のことを「お斎」と呼んできました。そして、食事をいただきながら、お念仏に出遇った慶びを、その場に集まった方々と語りあいました。そのため、亡き人を偲びながら、飲んだり食べたりすることを「お斎」というわけではなく、「お斎」も仏事のひとつととらえ、亡き人をご縁にして、阿弥陀如来の教えに出遇う場として大切にしております。
料理は「精進料理」じゃないといけないの?

インドのお釈迦様の教団では、自分のために殺されたものでなければ肉も魚も食べていました。仏教が中国に伝わって不殺生戒などの解釈から僧侶は肉食をしないこととなりました。日本でもその影響を受けています。ですから、お斎は精進料理が伝統ですが、昨今は肉や魚を含んだ料理が多くなっています。
精進料理とは、「殺生(生き物を殺すこと)」を避け、「煩悩(人を苦しめ、煩わせる心)」を刺激しないために生まれた料理です。「精進」とは仏教用語で、「ひたすら仏道に励む」という意味です。そこから「美食や肉食を避け」また、「粗食や菜食によって精神修養をする」ということが食事におけるに「精進」になります。
真宗大谷派では、亡き人をご縁に、「お斎」という「精進」の料理を通して、日ごろ忘れかけている、他のいのちを殺しいただかなければ生きてはいけない身である事実を問いかけていると考えます。これは、普段の食事でも同じことですが、仏事といわれる法要が勤まった後であるからこそ、改めてこの事実を確認し、いのちに支えられていることに思いを馳せる大切な場所にしております。
「献杯」をすることがあるけど、どうしたらいいの?

そもそも「献杯」とは、「(敬意を表して)さかずきを人にさすこと」とをさします。「お斎」をいただく前に、喪主、友人や親族など、亡くなった方にご縁のある方が、列席者へ挨拶とともに、お亡くなりになった方へさかずきを傾けることを献杯といいます。
真宗大谷派では、「お斎」を食べ物や飲み物を通していのちをいただき、そのいのちによって生かされていることを確認する大切な場所と考えております。そのため、献杯ではなく、「食前のことば」「食後のことば」を皆様で唱和しております(下記参照)。
〈食前のことば〉
み光のもと
われ今さいわいに
この浄き食をうく
いただきます
〈食後のことば〉
われ今
この浄き食を終りて
心ゆたかに力身にみつ
ごちそうさま